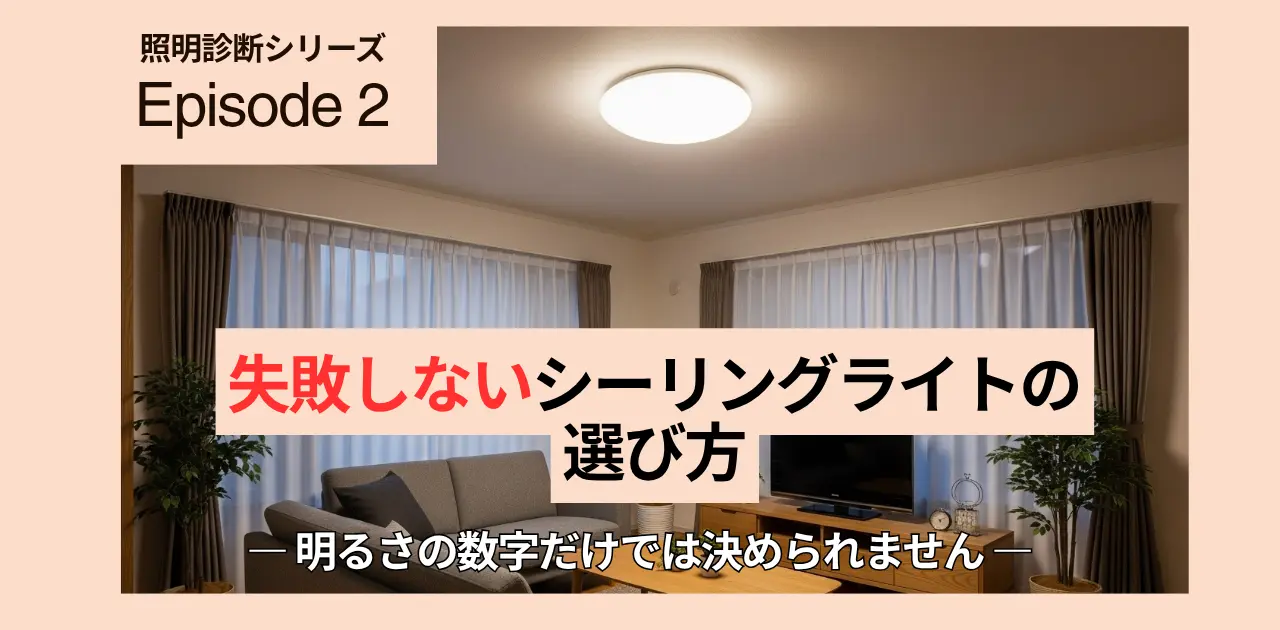──明るさの数字だけでは決められません
🏠 はじめに
前回のブログで「冬の不調は光のバランスが関係しているかも?」とお話ししました。
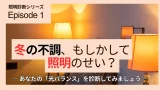
今回はその続編として、実際にどんな照明を選べば快適に過ごせるのか――
とくに家庭で最も多く使われている 「シーリングライト」 に焦点を当てて解説します。
「8畳用を買ったのに暗い」
「明るいはずなのに落ち着かない」
そんな経験はありませんか?
実は、明るさの感じ方は数字だけでは決まらないのです。
部屋の構造や光の色、壁の色まで含めて考えると、初めてちょうどいい明るさにたどり着けます。
■ シーリングライトの明るさを決める「ルーメン」の目安
照明器具には「明るさ◯lm(ルーメン)」と書かれています。
このルーメンは光の量を示す数値で、
「どれだけ明るい光を出しているか」を表しています。
しかし実際の明るさ(照度)はルクス(lx)で測られます。
ルクスは「光がどれだけ届いているか」を示すため、
天井の高さや光の広がり方によって同じルーメンでも体感が変わるのです。
| 部屋の広さ | 推奨ルーメン(lm) | 明るさの印象 |
|---|---|---|
| 6畳 | 約2,000〜3,000lm | 落ち着いた明るさ |
| 8畳 | 約3,000〜4,000lm | 一般的な明るさ |
| 10畳 | 約4,000〜5,000lm | しっかり明るい |
| 12畳以上 | 約5,000lm〜 | 広いリビング向け |
💡ワンポイント
壁や床がダークカラーの部屋は光を吸収しやすいため、
ワンランク上の明るさを選ぶのがポイントです。
■ 光の色(色温度)で空間の印象が変わる
シーリングライトは光の色によっても印象が大きく変わります。
| 種類 | 色温度 | 特徴 |
|---|---|---|
| 昼光色(6500K) | 青白い光。非常に明るく感じるが、くつろぎには不向き。 | |
| 昼白色(5000K) | 自然光に近い。作業にもリビングにも使いやすい万能型。 | |
| 電球色(2700K) | 暖かみのあるオレンジ光。リラックス空間向けだが少し暗め。 |
白っぽい光は「作業向き」、オレンジ系の光は「くつろぎ向き」です。
夜にリラックスしたい空間(寝室・リビング)は電球色、仕事や勉強、キッチンなど手元の明るさが重要な場所は昼白色が向いています。
💡最近はリモコンで色を切り替えられる「調光・調色タイプ」も人気。
朝は白っぽく、夜は暖かく、一台で生活リズムを整えられます。
■ シーリングライトの形状でも光の広がりが違う
- 拡散型:最も一般的で、光が均一に広がる。
- 集光型:下方向が明るく、読書や作業スペースに向く。
- 間接光タイプ:天井に反射してやわらかい雰囲気を演出。
たとえばリビングなら間接光タイプ、ダイニングテーブルやデスク上なら集光型など、部屋の用途に合わせて選ぶのがコツです。
■ 明るい部屋・暗くてもいい部屋
明るさの必要度は「部屋の役割」で変わります。
| 明るい方が快適な部屋 | 暗めでも落ち着く部屋 |
|---|---|
| リビング・キッチン・勉強部屋 | 寝室・トイレ・浴室 |
特にトイレや浴室はダウンライトやブラケット照明が多く、
強すぎないやさしい光が快適です。
■ 実はルーメンだけでは足りない理由
販売されている照明はルーメン表記が基本ですが、私たちが感じる明るさは「手元でどれだけ光が届いているか(ルクス)」です。
たとえば、同じ3,000lmでも天井が高い部屋では暗く感じます。
つまり、照明を選ぶときは 「ルーメン+部屋の条件」 を考慮することが大切。
迷ったら、調光付きや明るさセンサー付きの製品を選ぶと失敗が少なくなります。
■ 自分の好みを知るのも大事
明るい空間が落ち着く人もいれば、少し暗い方が安心する人もいます。
「ちょうどいい明るさ」は人によって違うため、暮らし方や時間帯に合わせて調整できる照明を選ぶと快適です。
■ まとめ
- シーリングライトは「ルーメン=明るさ」ではない
- 光の色・部屋の広さ・壁の色で体感が変わる
- 調光・調色機能があると失敗しにくい
- 明るさの基準を知り、自分の“心地よさ”を大切に
照明は、ただ部屋を照らす道具ではありません。
暮らしのリズムや気分を整える「環境づくりの一部」です。
明るさの数字だけで選ばず、自分らしい光を見つけてみてください。
🔧 最後まで読んでいただきましてありがとうございます
東京都足立区の電気工事店「でんきのひがき屋」の檜垣(ひがき)がお届けしました。
電気のお困りごとがあれば、
LINE公式アカウントからお気軽にご相談ください!
初回工事限定で「10%OFFクーポン」を配布中です✨
▼ LINEで友だち登録はこちら ▼